近年、Webマーケティングが複雑化する中でユーザーの購買行動は変容し、今やペイドメディア(Web広告)に対する慣れや不信感は高まっています。
そんな中で注目を集めているのが、広告感の薄い情報発信でファンを創出するオウンドメディアの存在。特にブログは人気の手法で、お手軽なイメージから「ちゃちゃっと更新をお願い」と運用を任される人も少なくないようです。
ですが、会社ブログで成果を出すのは簡単ではありません。運用目的に沿った内容で継続的に記事を制作し、PDCAを回していく。長期的なコストとリソースが必要ですし、何より続けるためにはネタ切れを起こさないような運用が大切です。
今回は会社ブログの書き方について、特に重要なネタ出しを中心に、具体的なアウトプット方法を解説します。
ちなみに、今回の記事で「会社ブログ」としているものは、新しくメディア構築するなどの大がかりなものではなく、今あるコーポレートサイト内のブログや既存サービス(noteなど)を活用することを想定しています。
目次
運用目的別!会社ブログのネタ探しポイントを解説
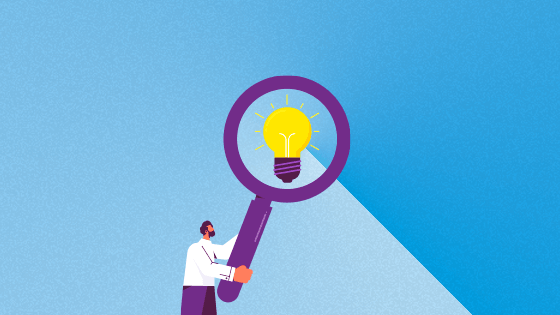
運用目的ごとにネタ探しの着眼点は異なる
会社ブログは「企業が発信するブログ」です。個人が運営する趣味ブログと異なるのは、長い目で見て会社の売り上げ、ファンづくりに貢献する内容であること。
ブログは読者にとっては気軽な読みものですが、作る側にとっては決して「なんとなく」でお手軽に作成できるものではありません。コンテンツの質・量を担保していくには、運営目的に沿った適確な情報を発信することが重要です。
一般的に、会社ブログの運用目的は次の4つに分けることができます。
- 集客
- ブランディング
- 採用
- 教育
あなたの会社の目的はどれにあたるでしょうか。
企業によっては目的が単独のこともあれば、複合パターンの場合もあるでしょう。もし目的が明確でない場合、方向性が定まらずに記事のネタ探しが難しくなるばかりか、ブログ自体が成果の見込めない存在となってしまいます。
運用目的を明確にする重要性と目的別のメリット・考え方については過去記事で解説していますので参考にしてみてください。
次からは、ネタ探しに関して目的別でヒントを見ていきましょう。
会社ブログ「集客」目的のネタ探し
会社ブログの中でも運用目的として多いのが「集客」ではないでしょうか。
集客が目的の場合は、ずばり商品やサービスの良さを直接的/間接的に紹介する記事を柱にしましょう。見込み顧客、はっきりとしたニーズを持たない潜在顧客、などの検討フェーズを意識した発信に絞ることが大切です。
ネタ探しには、営業担当者からの情報収集が有効。ユーザーの需要やトレンド、お客様の傾向などを把握しているはずですから、キーワードに注目すればネタが見つかります。
他には、カスタマーサポート部門にどういった内容のお問い合わせが多いか尋ねたり、商品を使用したお客様の声を情報共有してもらったりするのもおすすめです。一般の製品紹介ではふれていない詳細スペックを紹介したり、製品をさまざまな角度から写した写真を掲載したりと、ユーザーのお悩みや期待に寄り添う話題を提供できるはずです。動きのある商品なら、動画があると、商品を手に取ったときのイメージがグッと具体的になっていいですね。
開発部門や製造部門から製品愛や専門性、開発秘話などを引き出せれば、興味深い話題を提供できるでしょう。
集客に向けたブログを運用すれば、自然と製品データを蓄積することとなり、製品紹介ページを改修する際の強力なデータとなる点もメリットです。
会社ブログ「ブランディング」目的のネタ探し
ブランディングとは、商品や企業の価値を感じてもらい他社との差別化を図ること。ブランディング目的の会社ブログ運営は集客を目的とする場合と似ています。ネタ出しの方向性も、集客目的と同じく見込み顧客を意識した発信を心がけましょう。
加えるべき要素としては、商材のアピールだけでなく製品やサービスに込めた“こだわり”や“願い”を重視すること。そう考えると、売り上げ貢献などはいったん脇に置き、内面に訴えかけるような熱を帯びた発信、マニアックな情報提供などが効果的といえるでしょう。時には思い切って「誰が興味あるの?」と首をかしげるようなピンポイントなネタもを提供してみるのも大いにアリ。刺さる人には刺さり、大きなインパクトを残します。
信頼感や共感、驚き、または「手に入れたい」というあこがれを抱いてもらうことにより、ブランド価値が高まっていきます。
会社ブログ「採用」目的のネタ探し
近年増えているのが採用目的の会社ブログ。求職者を対象に、業務内容や企業文化が伝わる情報を発信します。記事のスタイルとしては、社員インタビューや社内行事・社内制度(福利厚生など)の紹介がスタンダードなかたち。読者が「ここで働く姿」をイメージできるネタの発信に努めましょう。
採用目的の会社ブログの場合、社内のさまざまな人・行事にふれるため、重要になってくるのが素材集めです。多くの部署の協力が必要になりますから、担当者は特にフットワークの軽さが成功のカギになりますよ。
社内行事はすぐ記事にする/しないにかかわらず写真を撮っておくとネタのストックになりますし、社内制度の紹介なら活用事例がわかる写真やデータを示せるよう手配することが欠かせません。社内行事に関しては全社ミーティングや周年イベント、社内サークルの活動風景をこまめに撮影する。社内制度に関しては、長期休暇をアピールするなら利用者に期間中のスナップを依頼するなど、日頃からアンテナを張っておくことが大切です。
ここで、多くの企業が実施している社員インタビューについてポイントをまとめておきます。まず、可能であれば職種も年齢もワークスタイルもさまざまな人材をたくさん見せられることが理想です。そして、それぞれの働きぶりや応募者が知りたいであろう話題を引き出せるようインタビューを実施しましょう。専門性の高い部署なら、研究内容や外部との関わりなども含めて紹介できるとなお良し。
社内でインタビューを行う場合、ともすると雑談に偏りがちなので、質問事項の準備や事前説明などきちんと段取りすることがポイントです。
会社ブログ「教育」目的のネタ探し
ターゲット読者に向けた情報発信だけでなく、社員教育のツールとしてブログを活用する企業も多くなってきました。社員は情報を言語化してアウトプットすることで、ノウハウを定着化させることができ、同時に読者には知識を提供できる点にメリットがあります。
教育目的で会社ブログを運用する場合、複数社員でブログ記事投稿を持ち回りすることになるでしょう。各記事の具体的なネタはその時々の執筆者が決めるとして、ブログ運用の担当者はそのお手伝いができると制作がスムーズになります。
たとえば、閲覧数の多かった過去記事や他社の人気記事に関する情報を共有する。またはWeb検索の分析ツール(Googleサーチコンソールなど)を活用してキーワード候補を提案するなど、ネタのヒントになって喜ばれるでしょう。
円滑な運用には、情報が集まる協力体制を!
ここまで見てきたように、運用目的が4つのうちのいずれであったとしても、会社ブログのネタ出し・制作には関係社員や関連部門の協力が不可欠です。
息切れしない運用を続けていくには、担当者が自身の役割を周知しておくだけでなく、日頃からアンテナを広く張り、声をかけやすいようにしておく=社内情報が集まるようにしておくことが大切です。
Web制作・コンテンツ制作をご検討中の企業様、内製が負担になっている担当者様、「Web制作会社スプー」に、お気軽にお問い合わせください!
[流れ&ポイント解説]会社ブログの記事の書き方

書くネタが決まったら、ブログ記事を制作していきましょう。大きく3段階に分けて解説します。
STEP① 構成をつくる
内容が決まったからといって、文章をいきなり書き進めることはおすすめしません。
目的が伝わるブログとは「読みやすいブログ」です。そして読みやすいブログとは、主役(いちばん伝えたい情報)と脇役(メインの話題を盛り上げる情報)が明確で、主役を引き立たせるストーリーが存在します。このストーリーこそ、記事全体の構成のこと。
主役と脇役はネタ探しで準備できましたから、実際の制作工程ではまず構成を組み立て、記事の全体像を描きます。
構成を組み立てる際は、取り上げる話題をグループごとに章立てし「大見出し→小見出し→本文に書く要素」と箇条書きしていくと進めやすいですよ。
課題を解決できていることはもちろん、順序として読みやすいか、不足はないかなど確認しましょう。
ここで意識したいのが、自社しか持ちえないオリジナルの情報(一次情報)です。読者に気づきや目新しさを与える内容は、他社との差別化に大きく役立ちます。
もちろん、全編を通してオリジナルな内容で埋めるのが難しい場合もあるでしょうから、そういった場合は競合他社がどういった話題を取り上げているか調査してみるとヒントが見つかりますよ。
記事の流れが自然かどうか判断が難しい場合は、「大見出しだけを繋げたときに、記事のおおよその内容がわかるかどうか」を意識してみてください。
ページを訪れたユーザーが文章の隅から隅まで読んでくれるとは限りません。飛ばし読みのときに目印になる大見出しが理解しやすければ(または大見出しで“引き”をつくっておけば)、ユーザーが文章を読み込んでくれる確率は高まります。
STEP② 構成に沿って執筆する
構成が決まったら執筆に取りかかります。組み立てたストーリーに沿って、箇条書きしたテキストを肉づけ&繋げていきましょう。
執筆時の最大のポイントは、なるべく「ストレスなく読める文章」に仕上げることです。文章のはじまりから終わりまで、引っかかることなく読めて内容を理解できるかどうか。これが読後感に大きく影響します。
加えて、より多くの人に伝えるためには、難しいことを難しいままに書くことは控えましょう。
たとえば、採用目的の会社ブログで研究職の業務について発信する場合。専門的な話題を専門ワード満載で書いてしまっては、同じ分野を研究する人にしか伝わりません。ピンポイントな募集記事ならそれもアリです。しかし、同じ内容でも難しい部分をかみ砕いて表現できれば、異なる専門分野をもつ人やスタッフ部門を希望する人にも自社の研究内容をアピールする記事にできます。
会社ブログの運用目的が何であれ、掲載する内容はあなたの会社や商材の強みであるはずです。せっかくページを訪れた人が「よくわからないからもういいや」と離脱してしまわないように心を砕きましょう。これも読者に読むストレスを与えない方法の一つです。
他に、記事をユーザーの目に留まりやすくする手段としてはSEO対策がメジャーですが、SEOは競合記事の文字数をリサーチしたり、共起語、周辺後など考慮すべき要素が多岐にわたり繁雑です。本格的にSEO対策を考える場合は、記事の制作を専門会社に任せることをおすすめします。
STEP③ 挿絵や図を準備する
執筆にあたって「これはフロー図にした方がわかりやすいな」「表にした方が比較しやすいな」という内容があれば、積極的に実行しましょう。イラストや図解は伝えられる情報量も多いですし、印象に残りやすい点でも大きなメリットがあります。
「でもデザイナーがいないし、きれいな作画は難しい」という場合でも諦めないでください。最近は低価格でプロに依頼できるサービス(ココナラ、クラウドワークスなど)が増えてきました。活用してみてはいかがでしょうか。
オリジナルの画像は、記事のクオリティを飛躍的に高めてくれる頼もしい存在です。
「続けること」が最も難しい!?ブログ運用には体制が必須

一般的にブログ執筆といえば気軽にできそうなイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし、こと会社ブログに限っていえば一朝一夕で成果を出すのは容易ではありません。オウンドメディアとして運用するなら情報の蓄積、つまり継続することが重要です。
継続する上で必要になるのが、運用コスト・社員の労力・制作時間・社内の協力。担当者がブログ運用にしっかり専念できるように、社内体制を整えることが求められます。
継続的な運用コストが必要
オウンドメディアとはコンテンツを蓄積していくことで価値が高まっていくメディアです。
しっかり運用を続ければ企業の資産となり、Web広告なしに売り上げ向上やファン顧客獲得など大きな成果を生む武器となりますが、率直にいえば即効性は期待薄です。
決裁権を持つ人に「コストばかりかかる」と勘違いされないよう、「開始後しばらくは種まき期間で、目に見える効果は得られない」という点を関係者間で共有しましょう。
長期的な予算確保はマストといえます。
ありがちな失敗「更新が途絶える」はなぜ起こる?
これまで多くの企業様のオウンドメディア運用を見てきましたが、更新が途絶える要因の多くが「リソース不足」と「ネタ切れ」です。
担当者がネタを確保し、運用サイクルを回すことができるのは、全社員の理解と部門の垣根を越えた協力体制があってこそ。
質の低いコンテンツは、会社のファンを増やすどころか逆効果を生むことにも繋がります。もしリソース不足で社員の負担が増えるなら、外部に依頼できることは割り切って発注するのも一つの手です。
会社ブログの運用は意外と負担が大きい。スプーがお手伝いします
ここまでご覧いただいたように、オウンドメディアとして会社ブログを運用するにはコストも労力もかかり、ブログ担当者にさまざまな負担がかかります。
もしすべてを社内でまかなうことが難しい、または作業負担を抑えたいとお考えなら、外部のプロを巻き込んだチーム体制で運用することをおすすめします。

私たちスプーは、創業以来たくさんの企業様のオウンドメディア・Webコンテンツの企画・制作に携わってきました。
クライアント様企業を深く理解し、ネタ案出しから執筆、制作はもちろん成果分析などもお任せいただけます。
これから会社ブログを運用していきたいとお考えのマーケターの方、ご興味を持っていただけましたら、ぜひ制作実績をご覧ください。



